本日は前回に引き続き心房細動(AF)のなかの発作性心房細動(PAF・パフ)についてです。
言葉だけなら聞いたことがある方も多いと思います。
目次
発作性心房細動(PAF)とは
これは、基本調律が洞調律(SR)であった患者さんが急に心房細動(AF)へとリズムチェンジした場合をいい、その心房細動(AF)が数時間~7日程度で洞調律(SR)へと戻るものを発作性心房細動(PAF)といいます。
波形として記すとこうなります。

3拍目まではSRです。
しかし、その後はP波がなく、R-R間隔も不整です。AFへとリズムチェンジしたのですね。
こういった波形が示すものを発作性心房細動(PAF)といいます。
発作性心房細動(PAF)はトレンドグラフで特徴的なグラフとなります。覚えておくと判断材料となるのでオススメですよ。⇒心電図でのトレンドグラフの活用方法
AFはSRに比べると頻脈傾向となり、血圧低下やめまいといった症状が起こる場合があるためバイタルサインの観察が必要になります。
また、循環動態の変化によるさまざまな症状の出現が考えられるため、安静保持が必要となります。
もともとの基本調律がAFの患者さんの場合はワーファリンなどの抗凝固薬を導入していますが、急にPAFが発生した場合は血栓対策がとられていないことがほとんどです。
そのため、必要に応じてヘパリン点滴などの対応をしていくことになります。
心房細動の原因と発生多発部位について
原因については、加齢や甲状腺機能亢進症、虚血性心疾患、心臓弁膜症などがあります。
心房細動で、洞結節以外で電気刺激を発生しやすい場所として、左房に直結する肺静脈の付け根にある部位が知られています。
実は、新生児として生まれる前の胎児期には洞結節以外でも電気刺激を発生させる場所があるのです。(そのため、胎児は心拍数が速くなります。)しかし、出生と共に洞結節以外の電気刺激発生部位はその機能を停止します。
左房に直結する肺静脈の付け根にある部位は胎児期に、電気刺激を発生させる機能のあった場所で、再び電気刺激を発生し始めるのです。
発作性心房細動(PAF)のリスク
余談ですが、なぜ心房細動で心原性脳梗塞のリスクが高いかというと、AFの場合は左心房にある左心耳という場所で血流が滞りやすく血栓が形成されやすいためです。
左心房で形成された血栓が心室へ移動し、大動脈を経て全身へ流れてしまいます。
脳梗塞の合併症が多いのですが、もちろん血栓が流れていき詰まってしまった場所に梗塞が生じてしまうため全身の観察が必要です。
また、加齢による心臓の変化により発作性心房細動(PAF)の状態であっても、発症やその持続時間が長くなってしまい、慢性的な心房細動(AF)へと移行してしまうこともあります。
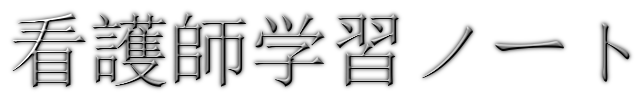
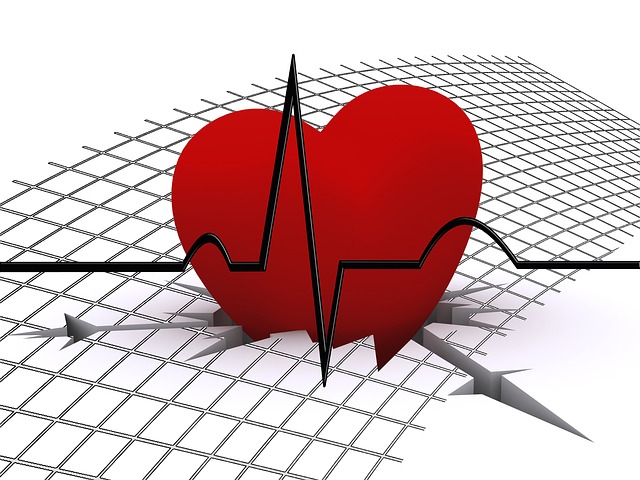












コメントを残す