ペースメーカーのフェラー①ペーシング不全
ペースメーカーを植込みしている患者に対して、モニター観察する場合どんなことに注目するでしょうか? 観察する項目は何点かあると思います。 しかし、一番大切なことはフェラーがないかということです。 フェラーとは、何らかの原因…
 ペースメーカー
ペースメーカー
ペースメーカーを植込みしている患者に対して、モニター観察する場合どんなことに注目するでしょうか? 観察する項目は何点かあると思います。 しかし、一番大切なことはフェラーがないかということです。 フェラーとは、何らかの原因…
 検査データ
検査データ
心エコーって難しいですよね。 勉強してみたい気持ちはあっても、なかなか気が乗らないなんてことも多々あると思います。 そこで、最低ここを覚えておけば大丈夫という部分をまとめてみました。 心エコーについて学び、日々の看護に活…
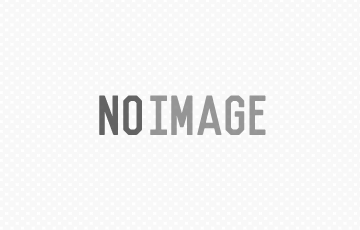 小児
小児
【病態】 《特発性血小板減少性紫斑病(ITP)》 何らかの原因によって自己の血小板を破壊する抗体(血小板付着抗体とよばれる免疫グロブリン)が生成され、それによって血液中の血小板の数が著しく減少する病気です。 ITPは急性…
 人工呼吸器と酸素療法
人工呼吸器と酸素療法
病院では酸素による治療を行っている患者が多くいますよね。 ドラマなどでも酸素マスクなどによる治療シーンがあり、よく知られているものだと思います。 そんな酸素療法も有効に使用される分には問題ありませんが、時には弊害といえる…
 コラム
コラム
私ハッカ油は、漫画が好きでよく読んでおります。好きなジャンルとしては、ダントツでバトルものですね。 実は私の妻も漫画が好きです。 好みの違うジャンルの妻のオススメする漫画は意外と面白いものばかり。アニメ化やドラマ化するも…
 コラム
コラム
感染予防のためにうがい・手洗いをしましょう!! よくそんなことをいいますよね。 しかし、冬に流行するインフルエンザにはどうなんでしょう?? 実はインフルエンザには効果がないのでは?? といわれているマスクやうがいについて…
 小児
小児
【病態】 小児の大部分はウイルスや細菌の腸管感染によってひき起こされる救性感染性下痢症です。 原因ウイルスとしてはロタウイルス、アデノウイルス、Norwalk Virusnadoなどが多いですが、圧倒的に頻度が多いのがロ…
 心電図の基本
心電図の基本
トレンドグラフとは トレンドグラフという言葉を聞いたことはあるでしょうか? 実は、心電図モニターには心電図装着患者の心拍数を時系列に表示する機能があります。 それが、トレンドグラフという機能です。 &nbs…
 心電図の豆知識
心電図の豆知識
以前、後輩看護師にPACとPVCの違いが分からないと言われたことがあります。 略語ではAとVが違うだけですし 上室性?心室性? 何が違うのでしょうか? そんな感じで、確かに分かりにくいですよね。 今回は、そんなPACとP…
 排泄ケア
排泄ケア
今回は病院で処方される便秘の際の下剤についてまとめてみました。 便を出しやすくするといっても、さまざまな作用により差があります。 今回は、処方される下剤が身体にどのように作用し便が出やすくなるかを簡単にまとめてみました。…